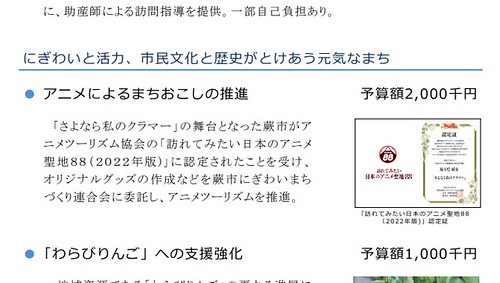令和6年(2024年)3月24日、東京ビッグサイトに、東京モーターサイクルショー見に行ってきた。
参戦するのは何年ぶりだろうか?
15年ぶりくらい?
二輪の免許を持っていない(それどころかクルマの免許もAT限定免許しか持っていないという、でもカドヤの革ジャンを持っているという)妻とタンデムでお台場へ。
ごくたまに取れる貴重な休みの日に、日帰りでどこかにツーに行ったとする。
例えば、伊豆やら、日光金精峠やら、道志みちやら。
道の駅で休憩しているバイクは大型ばっかりだし、乗っているのはコミネマンのようなウェアリングのおっさんばっかりだ。
(もちろん、私自身もその一人である)
なので、今、バイクに乗っているのはおっさんばっかりではないか、日本のバイク市場はおっさん消費のみによって成り立っているのではないか、今どきの若者は全くバイクに乗らないのではないか、と錯覚してしまう。
しかし、このモーターサイクルショー2024は、おっさんよりもむしろ、若者の姿の方が多かった。
展示バイクのランナップを見ても、若者をターゲティングしていることがよく分かる。
若者に見放されたら産業としては未来はないしね。
バイクって実はこんなに若者に人気があるんだな、と、おっさん層の一人としては、純粋に嬉しく感じた。
もう世間では、バイク乗りなんて絶滅危惧種なのかと勝手に思い込んでいた。
こんなに人がたくさん来ているなんて、まあ、嬉しいといえば嬉しい。
一緒に行った妻が、あれこれ試しにまたがっている私を撮影してくれた。
イタルジェット。
実物初めて見た!
街で走っている姿は一度も見たことがない。
イタ車の色はいいね。
すげーかっちょいいけど、洗車が大変そうだし、スクータなのに積載性ゼロ。
200ccで814,000円。
フォルツァやX-MAXからプラス10万円と考えれば、外車だし、それほど高い感じはしない。積載性ゼロだけど。しかも、おそらくすぐあちこち壊れるw
本田技研のブースへ。
CBR1000RR-R Fireblade。
2000年式逆輸入車、2006年式国内フルパワー化と、乗り継いだけど、ポジションの違和感ゼロ。
むしろコンパクトになって、乗りやすそうな感じ。
まあ、実際には、乗りこなせるイメージはまったく無い。
それにしても、この界隈のSSトップエンドモデルは、高くなった。昔は、120万円くらいで乗れたのにね。
今は250万円。
NX400。
意外と車格がでかい。しかし、400なのでそれなりに小さい。余裕がある。
これが「上がりのバイク」かもしれん。
ハーレー。
興味ないジャンルだけど、一応またがってみた。
やっぱり興味沸かない。
このジャンルにさっぱり興味が沸かないことに対して、ちょっとホッとするw
ヤマハのブースへ。
XSR900GPの往年のワークスレプリカ。
このカラーリングは、個人的にはぐっとくる。
しかし、中身は所詮はXSR900なんだよなあ、と考えると、あまり乗りたいとは思わないかな。
ナイケン。
初めて実車にまたがってみた。
フロント・リヤともに固定されているけど、またがっただけで、フロントヘビーな感じがよく分かる。うーん、なんとも。これは走ってみないと分からないな。
Tenere。
やはりテネレは憧れる。
しかし、車格がでかい。足つきわろし。乗れなくはないけど、街乗りはきつい。そもそも、日本の林道を走るバイクではないな、砂漠をかっ飛ばすバイクだ。
シート高875mm。
昔乗っていたCRM250ARの895mmよりは低いけど、シートの幅があるので、足つき性は同じくらいかな。
MT-09の3気筒のカットモデル。
ちょうど今乗っているやつ。
TMAX560 tech max。
いいねえ。
しかし、どういう人が、どういう乗り方するんだろう、このバイク?
お金が腐るほどある人がゲタバイクとして使うんだろうか?
取り回し悪いし、止める場所確保しにくいし、街乗りでは大変だと思うけどね。
TMAXというと、やはり、「ノリックが事故って死んだバイク」と連想してしまう。
川崎重工のブースへ。
NINJA 1000SX。
コンパクトで、ポジションがゆったりしている。
これは、かっ飛びバイクではなくて、上がりバイクかな。
メグロS1。
W230と共通のプラットフォーム。
エストレヤの後継か。
いいねえ。こういう小排気量シングルに、最近は興味が向く。やはり年なんだろうと思う。
KLX230。
ライトカウルがまともになったw
先代のライトカウルは、気持ち悪過ぎたww
スズキのブースへ。
スズキは、V-strom兄弟推し。
いいねえ。初代2014年式V-strom1000乗りとしては、嬉しい。
ファラオの怪鳥のクチバシデザインは秀逸。
今乗っているV-strom1000は、新車で乗り始めてそろそろ丸十年になるけど、まだまだしばらくは乗り続けるつもり。
GSX-S1000GT。
なにこれ、小っちぇ。
まあ、こういうのが乗りやすいんだろうな。これもNINJA 1000SXと同じ系統で、上がりバイクなんだろうな。
BMW motorradのブースへ。
BMWも一度は乗っておきたい。
この写真はF800GS。
乗りやすそう。
昔は、F650GSダカールに、ものすごく憧れたが、今は国産メーカがあれこれアドベンチャーモデルを出しているし、そもそも今V-strom1000に乗っているので、今さらBMWのこのジャンルに乗りたいとは思わない。
F900GS。
なにこれ、シート高、たか!
足つかないw
EVバイクの、CE04。
うーん。致命的にダサい。
まったく興味が沸かない。
トライアンフのボンネビル。
うん、たしかにかっこいい。
値段も手頃。
20年くらい前に、当時の福田モーター商会が笹塚にあった時に試乗させてもらったのだけど、ペダル位置が左右非対称である点に強く違和感を感じたものだ。
最新のモデルも、この点は変わらず。
かっこいんだけど、でも、これに乗るくらいなら、川崎重工W800でいいかな。
オレンジ君のKTMのブースへ。
1290 Super Adventureにまたがってみる。
意外と小さいのね。
R1250GSと比べてもかなり小さい感じ。
R1250GSやF900GSは大き過ぎて乗りこなせるイメージが沸かないけど、KTM1290 Super Adventureは、ふつうに乗れそう。
何? このかわいらしい電動バイク。
ぐぐってみたら、TROMOXという名の中華ブランドだった。
デザインは悪くない。かわいい。
値段も安い。
試しに衝動買いしたくなる価格だけど、中華製のバッテリは怖いよなあ。
TROMOXの電動スク。
かわいい。
でも、買うのは怖い。
モーターショー全体を通じて、EVの展示は少なかった。
いやー、楽しかった!
キャンギャルと写真撮りました。