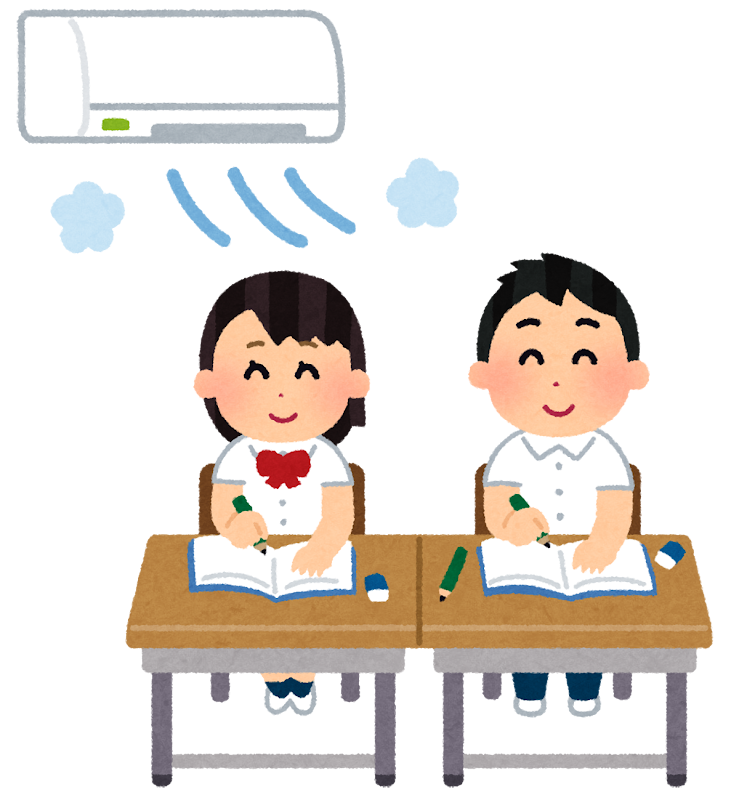私が所属している蕨市議会の保守系会派:令政クラブと、須賀敬史県議会議員と合同で、お隣りの戸田市の教育について、戸田市教育長に話を伺いに行って来ました。
戸田市の教育、というと、何となく先進的なイメージがあります。
また、豊かな財政を背景として、湯水のように教育にお金を注ぎ込んでいるイメージもあります。
しかしながら、これらはあくまでもイメージであって、実態はどうなのかな?
今までは体系的に戸田市の教育を調べてみたことはなかったのですが、この機会に、ざっくりとした戸田市の教育の特徴を把握することが出来たような気がします。
あくまでざっくりですけど、ポイントは、私なりには以下のように理解しました。
- 従来型の受験・進学のための暗記型教育を脱した、「考える力の育成」志向
- 民間企業CSRとのコラボによる、安上がりな新しい教育ツール・メソッドの導入
- 教育長の教育改革の方向性と、市長の教育に比重を置く姿勢との相乗
一つずつ以下に解説していきます。
- 従来型の受験・進学のための暗記型教育を脱した、「考える力の育成」志向
学校教育においては、当たり前ですけど、受験・進学というのはとても大切で、教育の成果、教師の成果のかなりの部分は、受験・進学の成績によって評価されるという冷徹な現実があります。
その結果として、学校教育の全ては、受験・進学の成績の向上という目的のために最適化されてしまいます。
「そのツール・メソッドは、受験・進学に役に立つのか?」ということが常に厳しく問われる、ということです。逆に、受験・進学に役に立たないのであれば、ムダだとみなされてしまいがちです。
しかしながら、受験システムは、年々変化しているとのこと。
今日では、東京大学の入試ですら、推薦入試が取り入れられています。
教育長曰く、むしろ、現実の受験システムよりも、一般の人の感覚の方が遅れているくらいだ、と。
つまり、受験・進学の成績の向上を目指すとしても、従来型の暗記型、ペーパー試験対策偏重の教育ではなく、「考える力の育成」こそが、実は今日、そして今後においては、より適しているのだ、という考え方です。
- 民間企業CSRとのコラボによる、安上がりな新しい教育ツール・メソッドの導入
多くの民間企業はCSRネタを探しており、特に教育分野での提供先を探しているとのこと。
自治体からアプローチすると、喜んで無償で教育ツール・メソッドを提供してくれる、と。コンピュータ端末をただで提供してくれたり、等。
戸田市は、様々な先進的な、実験的な、新しい教育ツール・メソッドの導入を行っておりますが、そのほとんどが、民間企業・大学等から無償で提供されているもので、ほとんどお金はかかっておらず、決して戸田市の豊富な財政力を背景としてお金を出して買ってきているものではない、とのことです。
近年の戸田市の一般会計予決算を見ると、教育費の比率がかなり高くなっているのですが、小中学校の校舎が順次更新時期を迎えており、建て替えを行っているためなのだそうです。
つまり、一時的に教育費比率が高まっているだけであり、その上積み分のほとんどは、ソフトウェア・教育の中身に対してではなく、ハードウェア・建物等に対してのものなのだそうです。
そして、新しい取り組みを行うにあたっては、ファーストペンギン・スピリットを大切にしているとのこと。
ファーストペンギンはかっこいいのですが、当たるも八卦、当たらぬも八卦の、バクチのようなベンチャービジネスの世界です。アザラシやシャチに食われて死屍累々たる結果になるリスクも覚悟の上で臨むのであればいいと思いますし、私もそういう世界で血を吐き泥水をすすりながら仕事をしてきたので、個人的にはその種のやり方には魅力を感じます。
しかしながら、子供たちの教育、子供たちの人生を実験台にすることになりはしないのか? ファーストペンギンではなく、二番煎じのフォロワーペンギンこそが、安価で効率的で、最も理想的な姿ではないのか? というのが私が感じた疑問です。
正直、戸田市のやり方は私には腹落ち出来ていないのですが、結果として、戸田市において、安価で効率的に、最先端の質の高い教育が提供されているのは事実であります。
- 教育長の教育改革の方向性と、市長の教育に比重を置く姿勢との相乗
現教育長が打ち出した、教育改革の方向性と、
・前市長の、教育へのICT導入を推進する姿勢
・現市長の、教育日本一を目指す方針
が、マッチしたからこそ、戸田市の教育改革が上手く進んだ、ということが言えそうです。
教育を変えるのは教育長、それをサポートするのが市長、という役割分担の中で、両者の方向性・方針が同じ方向を向いていたからこそ、ファーストペンギンとして先進的かつ試験的な挑戦をすることが出来た、と言えましょうか。