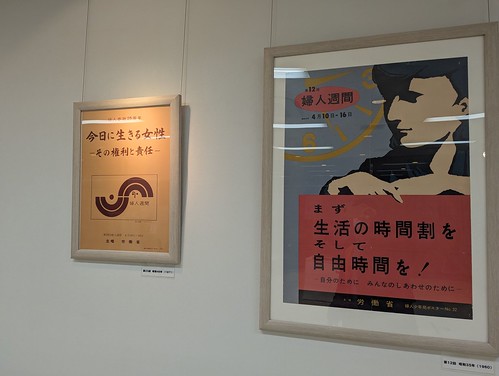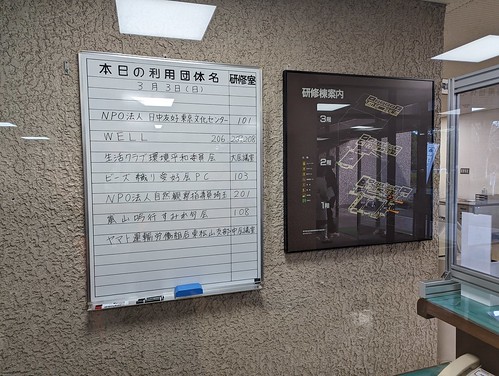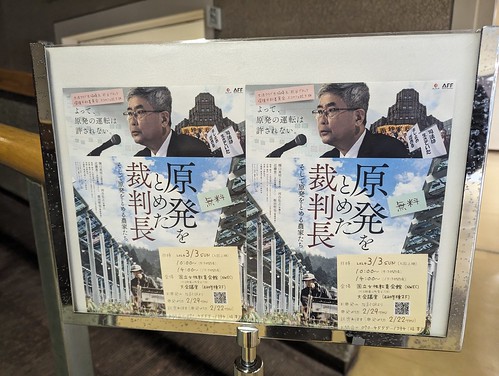緑川において、蕨市内の2階所で河川監視カメラが新設されています。
場所はこちら。
埼玉県 県土整備部の、さいたま県土整備事務所 管内の河川監視カメラの一覧です。
ページを開くと、最新の河川監視カメラ画像が閲覧できます。
当日0時00分から2分おきの画像が記録されているようです。それ以前の画像を遡ることは出来ないようです。
かなり解像度が荒い画像ですが、水面の高さは見られます。
夜間でもそれなりに明るく撮影出来るようです。
他の監視カメラ設置地点では、監視カメラによる画像データに加えて、cm単位の水位計を備え水位データまでも表示しているところもあります。
しかしながら、埼玉県 さいたま県土整備事務所に確認したところ、蕨市内の2地点に関しては、あくまでも簡易なものであり、画像データのみしか記録・掲載しないとのことでした。
その1 南町 桜並木末端部との合流地点近く
緑川と桜並木末端部との合流地点から、少し上流位置、右岸側に設置されています。
この写真は、下流側から上流に向けて撮影したもの。
この敷地は、緑川拡幅事業用地です。
太陽光発電設備を備えております。
「埼玉県 簡易型河川監視カメラ 太陽電池制御盤」と書いてあります。
上流側から下流に向けて撮影したもの。
緑川拡幅事業用地は、上記の以前の記事に記載した通り、耐水性舗装が施されています。
その2 塚越小 留守家庭児童指導室の横
緑川右岸の街路樹の中に設置されています。
下流側から上流に向けて撮影したもの。
左側の建物は、塚越小学校敷地内の、留守家庭児童指導室です。
「その1 南町」の河川監視カメラと同じように、ポール + 太陽光発電設備 + カメラですね。
よく見ると、緑川をまたいで、川の表面に向けて、何かの」機器が新たに設置されています。
拡大したところ。
川面に対して垂直に向けられています。
カメラでは無さそう。
水位を測定するセンサでしょうか。
このセンサの制御ボックス。
「機器名:水位計(危機管理型水位計)」と書いてあります。
上記webページ上には、あくまでも画像データしか掲載されておらず、水位データは表示されていません。
前述のように、管理者である埼玉県 さいたま県土整備事務所に確認しましたが、「あくまでも提供しているのは画像データのみであり、水位データは提供しない」とのことでした。
従って、何らかの実験的な機器か、平時においては稼働せず有事においてのみ稼働する機器ではないかと予想します。