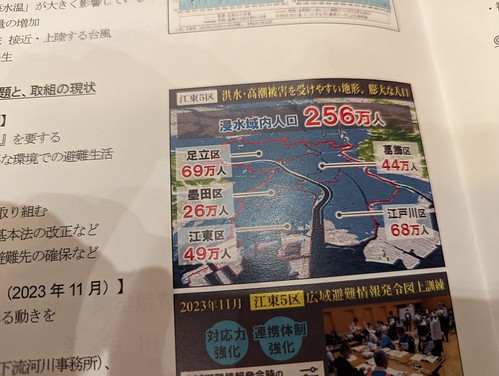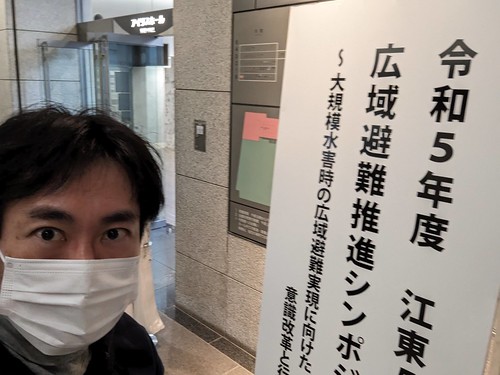本年、令和5年(2023年)9月8日から9日にかけて、茨城県・福島県沿岸の大雨は、大規模な被害をもたらしました。
お亡くなりになった方のご冥福をお祈り申し上げます。
被災した方々を衷心よりお見舞い申し上げます。
マスメディアの報道によると「台風13号による大雨」あるいは「線状降水帯による大雨」と、表記の揺れが見られます。
私の理解によると、台風と線状降水帯は、気象学的にはまったく別個の現象のはずです。
このあたりは、これから詳しく分析されていくものと思います。
9月10日、現地の被災状況を視察して参りました。
日立市河原小地区
沿岸に近い地域です。
海には、小さな漁港と海水浴場がありますが、漁業や観光の街という感じではないですね。住宅が密集した、住宅街です。

地域全域が水没したわけではなさそうです。
川の近くの、ごく一部の地域が水没したようで、道路は土砂が堆積していました。

橋のたもと部分の車道、川に沿った歩道のアスファルトが激しく削られてしまっています。

同じ位置から、カメラを右側(川側)にパンして撮影したもの。
氾濫したのは、こんな川です。
堤防もありませんし、川の敷地にすぐ隣接して民家が立ち並んでいます。

泥水を被った畳が、路上に山積みになっていました。
泥水に浸水すると、基本的には乾かしてももう使えません。

災害ゴミが野積みになっています。

エアコンの室外機が冠水したようです。
家屋の壁面には、泥の後がついていません。
この地域は、全体的に、泥の量がそれほど多くないのですよ。
つまり、川が氾濫して流れ出た水は、それほど土砂を含んでいなかったのではないかと予想します。
上流部で土砂崩れが起きたわけではなく、純粋に、河川が氾濫しただけ、ということのようです。

この川のちょっと上流部。
せいぜいこんな川。
水害は、
・内水氾濫(都市型水害、マンホールやドブが溢れるなど)
・外水氾濫(河川の氾濫、いわゆる洪水)
の2種類に分類されるのですが、これは河川の氾濫なので、外水氾濫ですね。

日立市ハザードマップ 洪水浸水想定区域(2023年9月時点)
河川の氾濫はまったく想定されていなかったことが分かります。

日立市ハザードマップ 内水浸水想定区域(2023年9月時点)
川の氾濫と言うよりも、川に沿ったごく一部の雨水排水機能がキャパオーバになることが想定されていました。
注意書きには、以下のように書いてあります。
想定最大規模降雨(1000年に1度の雨)により、既存の排水施設で処理しきれない内水が氾濫した場合に、想定される浸水区域及び水深を表示しています。
※「水防法」に基づくものではありません。
上の、橋のたもとのアスファルトがえぐれた部分は、黄色(0.5m-1.0m未満)になっています。
今回の雨量は、千年に一度クラスだったということですね。
日立市役所
TV報道では、呆然とした表情の市職員達がバケツリレーをして泥水をかき出す映像が流れていました。
日立市では、東日本大震災によって被災した市庁舎を、災害に強い建物に建て直したはずなのに、その新庁舎が被災してしまった、ということです。
災害に強い新庁舎をまさに今建設中で、竣工間近に控えている蕨市民としては、ショッキングでしたね。

日立市役所の全景。
上流部(山側)から望む。
建物手前の駐車場から道路にかけて、一面が水没したようで、土砂が堆積しています。

拡大したところ。
小さな2つの川が、市庁舎敷地の上部(山側)にて合流しています。

ここが氾濫した地点のようです。
2つの川が合流した後、この川は、上記写真の左端に写っているように、暗渠に流れていきます。
川の水面から、天端までは2-3mくらいありますが、堤防はありません。
人やクルマの落下防止のフェンスが設けられていたのみです。

上記の位置から、カメラを上流部(山側)にパンさせて撮影した写真。
数沢川。
写真左側(川の右岸)の建物は、日立メディカルセンター看護専門学校の校舎。
写真右側(川の左岸)の建物は、google mapには情報が載っていないのですが、校舎か寮か何かのような造りです。
さらに川の上流は、街区が整った住宅街です。
市庁舎の上流部には、氾濫した形跡はありませんでした。
氾濫したのは、あくまでも、市庁舎の真上地点のみだったようです。

市職員が泥をかき出したり、濡れたものを干したりしていました。

移動式ポンプで排水している。
まだ地下フロアの浸水は続いていたようです。
市庁舎が冠水した後、日立市の災害対策本部は、消防本部に移されたそうです。
この地域で停電が発生したわけではないようですが、地下に配置された受電設備、非常用発電装置が浸水し、市庁舎は停電したそうです。
地下に電気関係の設備を置いてはいけない、ということですね。

日立市ハザードマップ 内水浸水想定区域(2023年9月時点)
浸水がまったくの想定外ではなかった、ということが分かります。
今回の電源喪失は、想定外ではなく、想定内の出来事だった、ということですね。

市庁舎近くの、国道6号の歩道。
歩いて、消防本部へ。

市庁舎から、国道6号を挟んで斜め向かいに位置する、日立市消防本部。
かなりゆったりした造りの建物です。
敷地は広く、公園を兼ねた芝生が市民の憩いの場となっており、昼寝すると気持ちよさそうでした。

日立市消防本部の近く。
宮田川。
川がカーブする箇所で、外側が削れてしまったようです。
日立市白銀町地区
上記の、消防本部のすぐ脇を流れる宮田川を遡り、白銀町地区へ。

宮田川は、この白銀町地区では、局地的に氾濫したようです。

日立武道館。
大正6年、日立鉱山の福利厚生施設として建てられ、後に日立市に寄贈され、今は武道館として用いられています。
駐車場が災害ゴミ置き場となっていました。
いわき市 内郷白水町

福テレ

大雨から一夜 福島県での被害の爪痕あきらかに 穏やかな川が一変、濁流が住宅を...
https://www.fukushima-tv.co.jp/localnews/2023/09/2023090900000022.html
福島県に被害をもたらした大雨から一夜が明け、被害が徐々に明らかになった。<片付けに追われる住民>いわき市内郷白水町では、あらゆるものが押し流されていた。住民が「綺麗な透き通る水」と話す川が溢れ、周辺の...
再び常磐自動車道に乗って更に北上し、福島県いわき市へ。

新川にかかる橋。
水没したクルマをレッカー移動していました。
川には、大量の木々が引っかかっています。

この川は、堤防はありません。
川に沿った人家は全面的に床上浸水したようで、泥をかき出したり、家財道具を干したりしていました。

折り重なったクルマ。

橋に引っかかった木々。

道路上を覆い尽くした土砂はまだ濡れており、ぬるぬるして滑ります。

路面が乾いた箇所では、土埃が凄まじく、クルマが通るたびにもうもうと巻き上げられます。
それでは、この新川にかかる橋を中心とした、いわき市内郷白水町のハザードマップを見てみましょう。

国土交通省 重ねるハザードマップ いわき市内郷白水町 土砂災害(2023年9月時点)
川に沿った谷筋の集落だけに、土砂災害の危険性は指摘されていました。

国土交通省 重ねるハザードマップ いわき市内郷白水町 洪水(2023年9月時点)
しかしながら、新川が氾濫する可能性は、まったくの想定外だったようです。
堤防もないし、まさかこの川が氾濫するはずがない、と近隣住民は安心していたのではないでしょうか。

同じ川の、少し下流部に移動したところ。
この辺りは、氾濫していません。
しかしながら、クルマから降りると、すさまじい異臭がしました。
腐敗臭と違う。
どちらかと言うと、排泄物の臭いに近い。
しかし、おそらく、排泄物そのものではない。
よく、土砂崩れの前触れ現象の一つとして「異臭がすることがある」と言われるが、その類だったのではないでしょうか。
水没した白水阿弥陀堂

福テレ

「お堂の床上浸水が一番ショック」国宝・白水阿弥陀堂も浸水の被害 美しい光景が...
https://www.fukushima-tv.co.jp/localnews/2023/09/2023090900000018.html
大雨の被害は、いわき市内郷白水町にある国宝にも及んでいた。福島県唯一の国宝建造物に指定されている白水阿弥陀堂。普段は季節の花々が咲く、美しい光景が広がっているのだが、茶色い水に浸かっていた。<5時間の...
以前に行ったことはなく、初めて訪れました。
平安末期に建てられた、国宝指定の建物です。
池水浄土庭園の奥に阿弥陀堂があります。

浄土庭園は泥水で濁っていました。

阿弥陀堂は水没しています。

国土交通省 重ねるハザードマップ 白水阿弥陀堂 洪水(2023年9月時点)
5.0-10mの浸水が想定されていました。
標高が低いようですね。
いわき市 内郷宮町
少し北上して、内郷宮町地区へ。
内郷第二中学校では午後11時頃に体育館の床上が浸水したため、避難者の受け入れを停止した。4世帯6人がステージ上に移ったという。
避難所が床上浸水って、やばいですね。

内郷第二中学校
敷地内に入るのは遠慮しました。

敷地内は災害ゴミ置き場になっていました。
床上浸水した体育館。
決して、川に隣接しているわけでも、この集落の中で特別に低い位置にあるわけでもありません。

避難所である中学校体育館が床上浸水したくらいですから、この地域一帯が全面的に床上浸水したようです。

いわき市立宮小学校。
川から溢れた水・浮遊物が道路上を流れ、フェンスを押し倒したようです。

同じく、宮小学校。
流れてきたクルマが、フェンスを乗り上げる形で押し倒しています。

この地域に床上浸水をもたらした、宮川。
川の水面から天端までは、2-3mくらい。
堤防はありません。
川にすぐ隣接して、民家が建てられています。
それでは、この地域のハザードマップを見てみましょう。

国土交通省 重ねるハザードマップ いわき市内郷宮町 土砂災害(2023年9月時点)
上記画像内で、
川は左から右に流れています。
2つある学校マーク【文】のうち、
右側が、内郷第二中学校
左側が、宮小学校。
集落の後背には里山があり、土砂崩れの危険性が示されています。

国土交通省 重ねるハザードマップ いわき市内郷宮町 洪水(2023年9月時点)
なんと、宮川の洪水の可能性は、ハザードマップ上では示されていません。
ハザードマップは不完全
ということで、上記で見てきたように、河川が氾濫した箇所は、
ハザードマップ上で氾濫可能性が指摘され、想定浸水深の範囲内だったところもあれば、
ハザードマップ上では氾濫可能性は指摘されていなかったところもありました。
「ハザードマップがおかしい!」ということでは決してありません。
ハザードマップは、ある一定の前提条件の下での被害シミュレーションを示したものに過ぎません。
雨の降り方が一様ではないように、前提条件を決める要素には多くのものがあり、ありとあらゆる前提条件を想定して、ありとあらゆる全てのパターンのシミュレーションを行うことは、現実的ではありません。
しかしながら、分かってはいるのですが、ハザードマップが示すレベルを超えた被害が生じた、という事実は、猛烈にショッキングーであります。