まだ、「うちの市における政策案」という形で考えがまとまっているわけではありませんので、一般論として、郊外ベッドタウン都市の市議会レベルで、今の時点で考えるべきテーマはどんなことかな?というのを、だらだらと書いてみます。
要するに、以下は、精緻で体系的な意見・政策案という段階のものではなく、セルフブレストベースで考えながら書く、という感じです。
私としては、まだ何らの結論も出していませんので、ご意見あれば、お聞かせいただければ幸甚です。
市民への外出自粛の要請の類
これは、基本的には県レベルの話なので、市で出来ることはないかと思います。
市の職員が広報車を運転したり、ハンドマイクを持って歩き回ったりして、公園や繁華街などの人が集まっているところを巡回して外出自粛を呼びかけるべきだ、という意見も目にします。
これ、けっこう大変ですよ。
現場の職員は疲弊します。身が危険でもあります。
市レベルで、行政リソースが限られている中で、そこまでやる必要があるのだろうか?
防災無線、CATVの広報番組などの広報チャネルを用いて呼びかけるくらいなら、たいした追加的費用もかからないし、簡単に出来るかもしれません。
疫学的なアプローチ
これも、県レベルの話です。
市レベルで出来ることは、おそらく無いかと思います。
保健所は県が設置していますので。
(但し、中核市以上の市は、自前で保健所を設置していますので、自前である程度は考えないとならないですね。)
・・・と、思っていたのですが、
発熱外来の設置
ある方より、発熱外来を設置してはどうか?と提案を受けました。
感染の疑いがある症状が出た人たちを場所を分けて診療するため、東京・杉並区で病院の敷地に「発熱外来センター」のテントの設置が始まりました。 …
このような、病院や役所の駐車場などにテントを設置して、地元の医師会の協力を得て、輪番で医師会所属の医師に、新型コロナの疑いがある人の一次対応を専門に対応してもらう、というものです。
医療現場を守る効果があります。
これも、保健所レベルでないと、設置ができないのではないか?と思っていたのですが、
新型コロナウイルスの感染増加に対応する緊急事態宣言を受け、登米市は17日、発熱を訴える患者を他の患者から隔離した場所で診察する「発熱外来」を、登米市民病院の敷地内に設置する方向で登米市医師会と協議していることを明らかにした。県内の自治体で発熱外来を設置するのは登米市が初めて。 同市では17日現在、新型コロナウイルスの感染者は確認されていない。 市によると、市内の開業医から「通常診療をしながら…
登米市では、地元の医師会に協力を求めて、登米市民病院の敷地内に発熱外来を設置するそうです。
登米市は、政令指定都市でも中核市でもなく、人口7.8万(奇しくも蕨市と同じくらいですね)ですので、自前の保健所は持っていません。
保健所を自前で持っていなくても、地元の医師会の協力を得られれば、発熱外来を設置することは可能のようです。
蕨市の場合であれば、医師会は「蕨戸田市医師会」ということで、範囲が戸田市・蕨市となっておりますので、蕨市と戸田市とで協力して設置する、というのが現実的かもしれません。
これは、一つのプランとして要検討です。
次亜塩素酸水の無料配布
また、この方からは、除菌効果がある次亜塩素酸水を製造して、無料で配布してはどうか、という提案もいただきました。
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kenko/kansensho/1010556.html
海老名市では、無料配布しています。
数万円程度のキットを買えば、特に専門知識がなくても製造できるようです。
人的リソースに余裕があれば、これもありですが、配布方法をうまく考えないと、配布する際に三密を作ってしまうことになります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応の類
平成24年(2012年)公布の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて、全ての市町村は、新型インフルエンザへの対策の計画を作らなくてはならないことになっています。
https://www.city.warabi.saitama.jp/kenko/kenko/kansensho/1001850.html
蕨市でも、平成25年(2013年)に「蕨市新型インフルエンザ等対策行動計画」を作っています。
この法律は、本年、令和2年(2020年)3月に改正されて、この度の新型コロナにも適応されることになりました。
この蕨市の行動計画の中で、
・全市民に対する、優先順位をつけた上でのワクチンの住民接種
・生活関連物資の安定供給の確保
・遺体安置・火葬施設の確保
などは定められています。
この当たりは、それぞれが必要な段階になれば、担当部署が動き出すことになると思います。
市民個人/市内事業者への給付金の類
取り敢えず、国が、所得制限無しで一律、一人当たり10万円ずつ配ることが決まりました。
国のこの政策についても、ちょっといろいろ言いたいことはありますが、ここでは置いておきましょう。
国とは別に、市レベルでも独自に、市民個人あるいは市内事業者に給付金を配ろう、という動きが各自治体であります。
埼玉県川口市は、新型コロナウイルスの感染拡大で厳しい経営状況に陥っている小規模な事業者への緊急支援策として、独自に一律10万円を支給することを決めました。 川口市が一律10万円の支給の対象とするのは、製造業は従業員20人以下、商業やサービス業では従業員5人以下の小規模事業者で、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、経営が悪化するなかでも事業の継続を目指す事業者です。 …
例えば、川口市では、市内の小規模・零細事業者に、条件付きで、一律10万円の「支援金」を配布するそうです。
川口市は郊外ベッドタウンであると同時に「産業の街」でもあり、圧倒的多数の中小零細企業を抱えているという特殊性があります。
地方政治というのは、横並びでモノを考えて競い合う雰囲気があるので、当然、「ウチもやろう」という動きが出てくるはずです。
これについて、どう考えるべきか?
まず、配る相手としては、
・市民個人
・事業者(法人・個人事業主、フリーランスも含めて)
の両パターンがあります。
目的としては、
・生活を守るため
・地域経済を回すため・守るため
の両パターンがあります。
個人的には、こういう「お金を配る」って好きじゃないですね。どのようなパターンであれ、政府の介入って無条件に嫌いですね。
しかし、これは、個人的な「好き/嫌い」の話であって、
今、論ずるべきなのは、「必要かどうか、やるべきかどうか」という話です。
今は、それが必要であって、やるべき局面だろうか?
大規模な感染症の発生は、歴史上、何度も発生してきたものであって、そもそも予見できたリスクであったとも言えます。
この考え方に立って厳しい言い方をすると、事業者ならば商売をやる上で当然に見込んでおくべきリスクであったはずだし、個人ならば半年や一年分くらいの生活費はキャッシュで持っておきなよ、という話です。
他方で、ここまでの規模のものは、想定を遥かに超越したブラックスワンだとも言えます。
うーん、まあ、ブラックスワンですよね?
(それにしても、21世紀はブラックスワン多過ぎです)
今の状況を予見できたのは、ビル・ゲイツ氏くらいじゃないでしょうか。
市内の会社がバタバタと倒産されたら困る、失業を生むし、地域経済が壊滅するし、税収も減るから。経済を回すのは政府の仕事なので、支援するのは当然だ、という考えがあります。
他方で、
10万円なんて、社員が3,4人もいればあっという間に溶けてしまう程度の金額に過ぎないし、その後、結局盛り返せずに倒産するなら、配った10万円は死に金になってしまう、一時的な不満を和らげるだけのための無駄なバラマキに過ぎないじゃないか、という考えもあります。
それでは、100万円なら大丈夫なのか?
300万円なら?
あるいは、思い切って、売上減少分の全額補填なら大丈夫なのか?
いったい、いくら配れば、市内の倒産や失業の発生を防げるのか?
そもそも、そのお金はどこから出てくるの?
そもそも、いつまでコロナ禍による外出の自粛、経済の縮小が続くのか?
見通しにくいので、推計できません。
給付金について考えると頭が痛くなってきそうなので、ちょっと置いといて・・・
そもそも、市レベルの(広義の)経済政策における、ファーストプライオリティは何か?
市内企業の倒産を防ぐ、失業の発生を防ぐ、市民が住宅ローンが払えずに持ち家を手放さざるを得ないような事態を防ぐ、これはもちろん大事ですね。
とても大事です。
しかしながら、最も重要な、何よりも優先しなくてはならないこと、そして、これだけは実現しなくてはならないという最低限のこと、は何でしょうか?
「経済的な理由による自殺を防ぐ」
これじゃないでしょうかね?
どうでしょうか?
自殺対策
では、経済的な理由による自殺を防ぐためにはどうすればいいのか?
全ての市町村は、国からの要請で「自殺対策計画」というものを策定しております。
個人的には、自殺する理由と対策に、それほど地域差があるとは思えないのですが、とにかく、市町村がそれぞれ独自に対策計画を作ることになっています。
蕨市でも、
https://www.city.warabi.saitama.jp/kenko/shogaisha/seishin/1001966.html
「蕨市自殺対策計画」というものを、昨年、平成31年(2019年)3月に策定しています。
ここで書いてあることを、ざっくり斜め読みした上でまとめると、
市レベルで、経済的な理由による自殺を防ぐための対策は、
・生活保護制度
・生活困窮者自立支援制度
この2つです。
「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付」について の情報は本会トップページからご確認いただけます。 「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。 …
社協がやっている生活福祉資金
このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。
厚生労働省が直でやっている、小学校休業等対応助成金・支援金
【2020年4月13日発表資料差し替え】「中小企業 金融・給付金相談窓口」の直通番号を変更しました。また、「よくあるお問い合わせ」を更新しました。 【2020年4月9日発表資料差し替え】「よくあるお問い合わせ」を追記しました。 経済産業省は、令和2年度補正予算案の閣議決定を受け、これまでの資金繰りに関する相談に加え、「中小企業 金融・給付金相談窓口」において給付金関係の相談を受け付けます。 …
経済産業省がやっている、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象とした「資金繰り支援及び持続化給付金」
これらの、国レベル、県レベルの給付金・貸付金をフルに使ってもらい、貯蓄を全て吐き出し、持ち家や自家用車などの資産がある人はそれらを売り払い、それでも尚、生活が立ち行かない、という人にとっての、セーフティネットが、
・生活保護制度
・生活困窮者自立支援制度
となります。
市レベルでのファーストプライオリティは、この2つの制度が、しっかりと機能するように、漏れが生じないように、備えをしておくことではないか、と。
生活保護制度は、文字通り「最後の」セーフティネットですね。
不正受給が問題になる一方で、経済的に困窮して悲観し、生活保護の申請をする前に自殺を選ぶ人たちもいます。自ら経営する会社を潰すくらいなら死んだ方がましだ、という人たちもいます。コロナ禍でダメージを受けて、本当に生活保護が必要な状態に陥ってしまった場合は、自ら死を選ぶよりも、この制度を使ってもらうえるようにしなくてはなりません。
生活保護は、国の制度であり、言わば市は下請けで運用しています。
原資も、原則として全額が国から市に支払われることになっています(3/4が国庫負担金、1/4は地方交付税交付金として)。ケースワーカーの人件費などの事務経費も国から支払われます(地方交付税交付金として)。
生活困窮者自立支援制度というのは、2015年に新設され、「生活保護の一つ手前の制度」と言われています。サービスメニュは、市が独自に設けることとなっており、費用負担が自前のものもあります。内容はかなり幅広く、「貧困の連鎖を防ぐ」という視点での、子供の学習支援などもあります。
制度は既にあるのです。
これが、しっかり機能するように備えをしておくことが大切です。
生活保護増大への備え
この2つの制度の利用者数・総額が拡大することを想定して、準備しておくことが、今の時点では必要なわけですが、
特に、重要なのは、ケースワーカーの増員です。
前述のように、ケースワーカーの人件費は、地方交付税交付金として、国が負担しています。しかしながら、人は、結局のところ、市の職員がローテーションの一環として配属されていますので、来月から急に1人増やす、ということが簡単にできるものではありません。
(尚、資格が必要な専門職ではありません)
蕨市役所の当該部署を見渡してみると、若手の職員が多く配属されているようですね。
また、受給者80世帯につきケースワーカー1人を配属しなくてはならないことになっているのですが、一昨年6月時点でのケースワーカー人数は12人で、平均して1人当たり被保護世帯102世帯を担当しているとのことで、既にケースワーカーは3人強不足していることになります。
増員しておくことが必要かなと思いますね。
再び給付金の話へ戻る。ある程度の倒産・ある程度の失業への備え
やはり、
・生活の支援
は、ある程度は必要か。
難しいのは
・完全に公平にやるのは無理。
どこかで不公平は必ず生じる。不満が出てくる。
・スピードが重要。
熟議を重ねている余裕はない。
・妥当な金額、条件は分からない。
「出せる金額」ということで総額をスパッと決めて、それを割り算で一人当たり給付額を決めるようなアプローチしか取り得ないのではないか。
つくづく、危機のリーダーは大変ですね。
DV・児童虐待が増えることへの対応
既に、人々の心がささくれ立ってきつつあるのを、折々に感じます。
今後、先が見えない家こもり生活、収入減、資産の毀損、失業の恐怖が続けば、ますます人心が荒廃してくでしょう。
家族が一日中、家にいて顔を突き合わせていますので、危機を前にして、お互いの存在のありがたみを実感して結束が高まる家族がある一方で、ギスギスしてケンカばかりという家族も出てくるでしょう。
やはり、DV・児童虐待は増えるでしょうね。
今でも市レベルでの対策はしているのですが、一層の強化が必要になるかも。
オンライン教育どうするか
いつになったら小中学校が再開できるか分かりません。
オンライン授業、これはやるしかないです。
今、やらないという選択肢は無いのではないかと思料。
道具(コンピュータ、ネットワーク回線などの設備)もないし、ノウハウもない。お金もかかるし、本来なら、1年、2年といった長い時間をかけて導入すべきものですが、無いなりに考えて今すぐやるしかない。
いわゆるゆとり教育の時代に学校教育を受けた世代の学力の低さを揶揄して「ゆとり世代」と呼んだりしますが、今の小中学生が「コロナ世代は学力が低い」などと言われることは、これは何としても防ぎたい。
ちょっと考えてみますので、別稿にて。
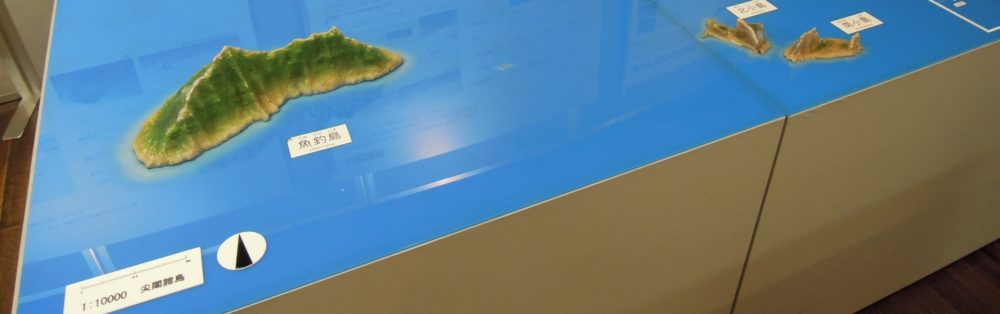
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16c3a22f.7d124444.16c3a230.08e0e4e6/?me_id=1213310&item_id=19424573&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9274%2F9784641149274.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9274%2F9784641149274.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

